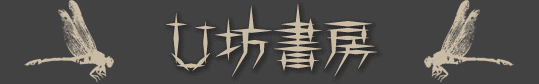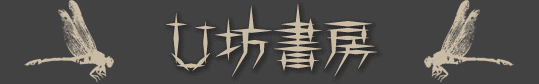2005. 2. 9(9歳)
作・U坊/リライト・Umiko
私は植物である。
このようなことを考えているとおり、私は考える草である。
しかし、ただ考えているだけで、身を守ることもできず、雨水を吸って生きているだけである。
幸い、私はこうしてここに生きている。
しかし、いつ人間どもが抜いてくるかわからない。
不幸なことに、私の周りには、家がたくさん並んでいる。
それらの住民たちは、いつ私を抜こうとするかわからない。
考える草の仲間は、残念ながらいない。
私だけが、草の中で考えているのだ。
はっきり言って、人間どもはまったく知能の低い、ただ生きている生物だ。
私は頭の中で、いろいろなことを思い、それを長い間考え続ける。
やがて答えが出てきて、私は、いろいろなことを知る。
人間がしていることは、私がしていることよりもずっと劣っている。
私はまず、考えることを覚えた。
ある嵐の日に、ちぎれそうになり、風を感じた。
その風の強さは、いつも感じている風よりも強く、嫌だと思った。
そこから、「嫌だ」という感情が生まれた。
そこで「嫌」の反対を考えた。それが、初めて考えたことだ。
人間どもが「いい」と言っている感情を自分で感じたことはないが、「嫌」の反対が「いい」であることは覚えた。
私は、人間どもが言っていることから、いろいろなことを覚え、それをかちゃかちゃと組み合わせていくうちに、気づけば人間以上になっていた。
しかし、私は動くこともできないただの植物だ。
だから、頭脳を試すこともできない。人間に伝えることもできない。
それでも私は、考え続けている。
やがて、人間どもが何か紙のようなものを読んでいることに気づいた。
それらは、「本」や「書物」というものだった。
中身はわからない。表紙さえも読めない。それを今、私は必死に考えている。
人間が、せめて題名だけでも口に出して読んでくれたら。
そこで、私はあることに気づいた。
「読んで欲しい」とか「言ってることがわかる」ということは、私は、ものが聞こえるのだ。
他の植物たちからは、ザワザワという音しか聞こえない。
そこで私は、ある疑問にぶつかった。
「なぜ、私はいるのだろうか」
それを思うと、なぜ、人間というものが存在するのか。
なぜ、「ここ」があるのか。
なぜ、この空間というものがあるのか。
この空間に果てはあるのか。
この空間ではない空間はあるのか。
いろんな疑問が浮かんできた。
もし仮に、他の空間があったとしたら、この空間をどう名付けようか。
人間どもは、このことをなんといっているのだろうか。
それとも、そんなことは考えてないのだろうか。
まったくわからない。
人間は、しゃべる。考えていることが音になる。
でも、こういうことは少しもしゃべらない。
なぜ、人間どもは、このようなことを考えないのだろうか。
そのうちに、人間どもがある行動をしていることに気づいた。
それは、いつも決まったときにソワソワすることだ。
人間どもは、そんなとき、「時間がない」と言っている。
「時間」とはなんだろう。
私はまた考えはじめた。
そのうちに、太陽が東から南へ南から西へ動いていった。
気づけば、あたりは真っ暗になっていた。
夜だ。
私は、暗闇の中で、「時間」とは何だろうと、考え続けていた。
一つの家の中から、「寝る時間」という言葉が流れてきた。
また「時間」だ。
私は時間というものが何なのかようやくわかった。
時間というのは、「あることをする」ときに決める「あるもの」。
しかし、それを何で計っているのかわからない。
なぜ、この世には「時間」があるのだろう。
さらに考えていくと、「時間」は本当にあるのだろうか。
ただ、人間どもが考えた空想にすぎないのではないか。
しかし、なぜそのような空想をするのだろうか。
そのとき、私は朝になるのを感じた。
時間が止まれば、あの太陽も止まるのではないか、と考えた。
何とかそのことを確かめたいが、そんなことはとてもできない。
私には、考えることしかできない。
「時間」に関しての知識は、私よりも人間の方がはるかに勝っている。
私は、だんだん「時間」は人間どもの空想に過ぎないと確信してきた。
風が吹いて、まわりの草がザワザワと言った。
時間が止まれば、風までが止まるのだろうか。
私の「なぜ」は広がっていった。
なぜ、私や人間どもは、ものを考えるのだろうかということも考えていた。
なぜ、他の草たちはものを考えないのだろうか。
それとも、考えていて、私が気づかないだけなのだろうか。
そして、こんなことまで考えはじめた。
なぜ、人間と植物に分かれているのだろうか。
人間以外にも動くものはあるのか。
なぜ、動くものと動かないものがあるのだろうか。
こうして、私は私の空想の中の未知の世界に連れ込まれてしまったのだ。
いや、空想じゃないのかもしれない。
もしかしたら、現実に他にも動くものがあるのかもしれない。
次の日には雨が降った。
私は、水をゴクンゴクンと飲みながら考えた。
この雨は生きているのだろうか。
生きているから動いているのだろうか。
それとも、風に乗って動いているだけだろうか。
あの雲の上には何があるのだろうか。
あの雲までもがこの空間の続きなのだろうか。
あの雲自体が、この空間に存在する物体で、その後も空間が続いているのだろうか。
もし、その空間があったとしたら、そこには何があるのだろうか。何もないのか、
真っ黒なのだろうか、真っ白なのだろうか。
人間は、なぜ、あんなに大きく、草はなぜこんなに小さいのだろうか。
この世は人間と植物だけなのだろうか。
このようなことを考えながら、考えはどんどん遠くへ広がっていった。
風というのは生きているのだろうか。
この空間は生きているのだろうか。
ここにあるものは、すべて生きているのだろうか。
土は生きているのだろうか。
土の下には何があるのだろうか。永久に土なのだろうか。
もしそうだとしたら、この地面こそ、空間の終わりなのだろうか。
次の日は、熱いほどの天気だった。
地面は砂になっていた。この砂は、水を吸い取ると土になる。
砂というのは水を吸い取る性質があるのではないだろうか。
もしそうだとしたら、どこまで水は届いているのだろうか。
永久に水なのだろうか。
人間たちが何か表情を変えていることに気づいた。
あるとき、一人の人間が、表情を変えていた。
それは、「楽しそうな」笑い方だった。
楽しそうな笑い方をするときには、楽しい、うれしいことがあったときなのだろう。
そのときだけなのだろうか。悲しいときには絶対に笑わないのだろうか。
「楽しい」とは何なんだろう。
「悲しい」とは何なんだろう。
そんなことは、私は体験したことがなかったのだ。
私はあることに気づいた。
考えるということは、「楽しい」のではないだろうか。
そのとき、私は、楽しい=考えると思ったしまったのだ。
人間どもは、わざわざあのような「車」などという機械を使って、考えに行くのだろうか。
もし、そうでないとしたら、他にどのような「楽しい」があるのだろうか。
人々はしゃべっている。人は、悲しいときでも楽しいときでも、絶対にものを考えているのではないかと思った。
楽しい=考える、
悲しい=考える
なのか。
そうして、また、私は考える。
なぜ、私は動かないのだろう。
なぜだろうか。なぜだろうか。なぜだろうか。
必死になって考えた。
あることに気づいた。
生き物というのは、動けるものと動けないものに分かれていて、動けるものを人間といい、動けないものを植物という。
しかし、動けるものは人間の他にもあるのではないか。
動けないものは植物の他にもあるのではないか。
動けるものは動けないものになぜ分かれているのかということについて、考えはじめた。
考えているうちに、ある考えが浮かび、とても怖くなった。
人間というものは、つまめば伸びるただの皮を持っているだけなのに、なぜ動いているのだろう。
私はただ緑色をしてただ薄っぺらい形をしているだけなのに、なぜ考えているのだろう。
なぜ、こんなものが生きているのか。
なぜ、生きていられるのだろう。
もし、人間が動けなくて植物が動けたら、どういう世の中になっていただろう。
人間が土に埋もれただじっとしている。
そして、植物はあの家などに住み、生活をする。
そんな世界に住んだら、私はとても幸せになるだろうと考えた。
私は、なんて不幸なんだろうと思った。
人間はなんて幸福なんだろうと思った。
どうしても、動けるようになりたい、
どうしても、動けるようになりたい、
どうしても、動けるようになりたい。
動けるようになるにはどうしたらいいのか、私は考えはじめた。
人間は、あの下の方についている二本の何かで歩いている。
人間どもは、あれを「足」とよんでいる。
あの「足」の右側を前に出し、次に左側を前に出し、そして歩いている。
植物でいえば、「根」がそれにあたる。
私は、根を動かしてみようとした。しかし、動かない。
植物とは、絶対に動かないようにできているのだとわかった。
そのとたん、私はとても悲しくなった。
私は、考えて、そして、悲しかった。
せめて、死ぬ前に動いてみたい。
自分の思うとおりでなくてもいいから、動いてみたい、
そんなふうに思った。
それから、早くも1年が経った。
時間という単位を覚えると、まったく便利だ。
ある日のこと、人間がこっちに近寄ってきた。
そして、私を引っこ抜いたのだ。
私は、人間に乗って、初めて動いた。初めて動いたのだ!
動くときには、前から風がビュービューと吹き、後ろの方に去っていった。
そのときの気持ちよさは何とも言えない。
私は、はじめて、「うれしい」と感じた。
「うれしい」ということを味わった。
そして、すぐに捨てられた。
まもなく、私は死んでしまったのであった。
今、死んだはずの私はここにいる。
なぜか、ここにいるのだ。
ここは、地面が砂や土ではなく、地面が白かった。
まわりには、いろいろな植物がいる。
私は、最後にあることに気づいた。
生き物は、死んだ後は、雲の上に行くのだ。ということ。
そして、私は雲の上で、生きているうちに解けなかったいろいろな謎について、今も考えている。
|
|
|