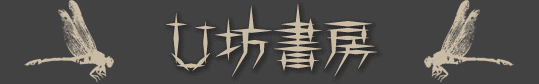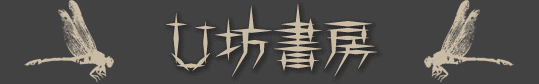・・その猿は自分のことを「我々」と呼ぶ
2003. 9. 14(8歳)
作・U坊/リライト・Umiko
我々は、猿である。
名前はまだない。
どこで生まれたかというと、ジャングルだ。
だが、故郷のジャングルは、なくなってしまった。仲間はいっぱいいたが、ジャングルとともに死んでしまった。
生き残ったのは、我々ただ一匹だ。
そして今は、日本に連れてこられて、この動物園で芸をしている。だが、失敗ばかりしていて、いつも園長にムチでたたかれている。
我々は、いつも逃げ出したいと思っている。
人間は、我々のことをリッキーと呼んでいる。だが、我々はその名前を捨てたいと思っている。だから、名前はまだないのだ。
ある日、いきなり飛行機が飛んできて、我々ただ一匹だけをのせて、どこか、砂がずっとある広いところにたどり着いた。
そこには、見たこともない風景が広がっていた。太陽がぎらぎらに照りつけていた。
少しも芸を覚えない我々を、園長はついに捨てることにしたのだろう。
飛行機は、我々ただ一匹を残して行ってしまった。
砂がいっぱいあって広いところ(砂漠)のずっと遠くには、建物があった。我々は、そこに近寄ろうとして一生懸命走ったが、どんなに走っても、その建物にはたどり着けなかった。
最後の力をふりしぼり、走って、走って、やっとその建物に着いた。
それは、三角の形をしていて、レンガで作ってあった。我々は、その建物をなんと呼ぶか迷って、「三角レンガ(ピラミッド)」と名付けた。
のどが渇いてきた。そのとき、向こうから、
「オアシス、オアシス!」
と、人間の声が聞こえてきた。行ってみると、水があった。
我々が、夢中になってごくごくと水を飲んでいると、人間たちがやってきて、
「生意気な猿め!」
と、追いかけてきた。
1メートル走ったか、2メートル走ったか、3メートル走ったか、4メートル走ったか、5メートル走ったか、そして、ついに、50メートルも走った。
そして、さっきの三角レンガ(ピラミッド)のところまでたどりついた。
全速力で走ったので、また、のどが渇いてしまった。でも、オアシスに戻ることはできない。我々は、三角レンガの中に入っていった。
三角レンガの中は、迷路のような道がずっと続いていた。
我々はその道をたどって、右に行こうか、左に行こうか迷いながら、右に行き、左に行き、行き止まりがあり、また元に戻ったりして、ようやく、細長い廊下までたどり着いた。
そこを越えてみると、人間が一人いた。気になったので、試しに、
「キキーッ! キキーッ!」
と、鳴いてみた。
その人間は、こちらを振り向いたが、すぐにまた向こうを向いてしまった。すごく年寄りの男だった。
そのおじいさんは、ずっとここに住んでいるようで、とてもボロい服を着ていた。
それで、我々は考えた。人間はあんなにぼろっちくても服を着ているのに、猿はなぜ服を着ていないのだろう。
1時間かかったか、2時間かかったか、ずっと考えたのだが、答えは浮かんでこなかった。
その人間を無視して、もう少し進んでみると、あたりは真っ暗になった。
水の音がしたので、そちらの方向に向かって進むと、水が通路を流れていた。飲んでみると、
「キキキーーーッ ぺっ」
ものすごくまずかった。
これは、ピラミッドができたときからここにある、紀元前の水だった。おいしいはずがなかった。
紀元前ということで、少し気になった。
なぜ、紀元前があるんだろうか。紀元前に生きていた人たちは、年代を数えにくくなかったのだろうか。
紀元前の一番最初を零年にして、今を1900年代か1800年代にすれば、紀元前はないことになるのに。
1時間かかったか、2時間かかったか、ずっと考えていたが、答えは浮かんでこなかった。
我々は、ピラミッドを出ることにした。
ピラミッドを出ると、前はぎらぎらだった太陽が、真っ赤になっていた。夕方だということがわかった。
ふと見ると、ピラミッドから人間が二人出てきた。一人は、さっきのおじいさんだった。
もう一人は、そのおじいさんにそっくりなおじいさんだった。二人が双子だということがわかった。
二人は、しばらく外にいて、またピラミッドの中に戻っていった。
これからどうやって暮らそうか、我々は考えた。
オアシスに戻れば、また人間に追い回されてしまう。でも、ここには草一本、木一本、小動物一匹いなかった。
故郷のジャングルに帰りたいと、我々は思った。
だが、よく見ると、木がいっぽんだけ生えていた。
この木はどこかで見たことがあった。思い出してみると、故郷のジャングルの木だった。
そして、オアシスの場所は、ジャングルの水の場所と同じだった。
今は砂漠になっているが、我々の今いるここには、川が流れていたはずだった。
我々は、砂を掘った。砂の中から、自分そっくりの骨が見つかった。
ここが、故郷のジャングルだということは間違いなかった。故郷のジャングルを探さなくても、ここがそうだとわかって喜んだ。
けれども、いくら故郷でも、こんなふうになってしまっては暮らせなかった。まだ日本にいた方がましだった。
そのとき、また飛行機が我々の目の前に着陸した。
そして、我々を乗せて、日本へ行った。いや、日本ではなかった。また別の外国だった。
外国人の一人が、我々を拾った。そして、ワーワー、ギャーギャー騒いでいた。どうやら英語で
「捕まえた、捕まえた!」
と、言っているようだった。
我々は、その人の家に連れて行かれた。家はとてもぼろぼろで、家の真ん中には深い穴があいていた。
我々は、その穴に、落とされた。
「キーキーッ」
と、鳴きながら、我々は深い穴に落ちていった。
ドスンッと穴の底に落ちたとき、そこは日本だった。
これまで見てきたのは、すべて夢だったのだ。長い夢だったので、不思議な気分だった。
そして、我々は、今日も動物園で芸をしている。
|
|
|